Archive for the ‘未分類’ Category
【動画】遺産分割協議書 作成の流れと注意点を解説します
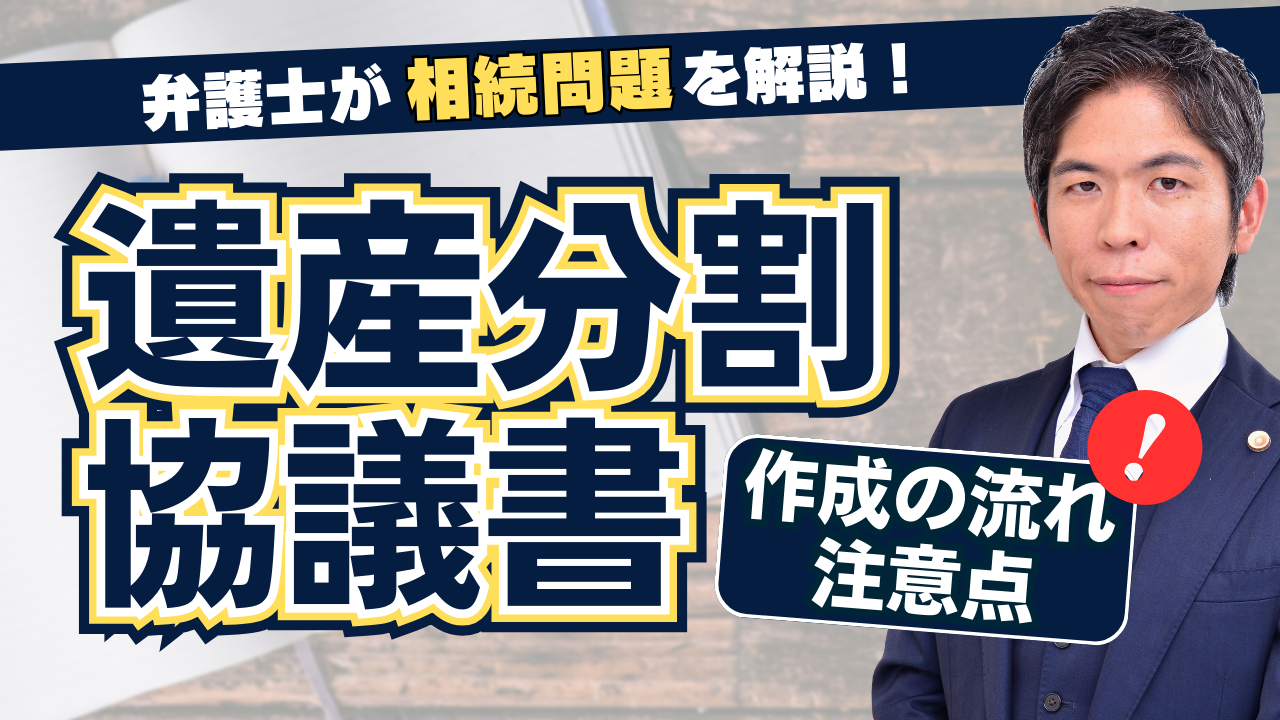
長瀬総合法律事務所の公式YouTubeチャンネル「リーガルメディアTV」にて、下記の動画を公開いたしました。
公開された動画
動画詳細
この動画は、ご自身で遺産分割協議書を作成しようと考えた場合に、まず注意して頂きたいポイントを解説しています。
そもそも遺産分割協議書が必要あるのかの判断方法、遺産分割協議書を作成する場合はどのような流れで作成すればよいか、作成する際にはどこに注意点をするべきなのかの3つのポイントに絞って、分かりやすく解説していきます。
チャプター
視聴時間:約14分
- 00:00:今回の動画は……
- 00:41:遺産分割協議書を作成する必要があるか
- 03:01:遺産分割協議書を作成する場合の流れ
- 06:55:遺産分割協議書の注意点
- 12:57:おわりに
お問い合わせはこちらから
当事務所では、現在のホームページのフォームからのお問い合わせのほか、お電話やLINE友だち登録、オンラインでの面談予約など、様々なご予約方法をご用意しております。お好みの方法で、ぜひお気軽にお問い合わせ下さい。
遺言書の書式・見本等
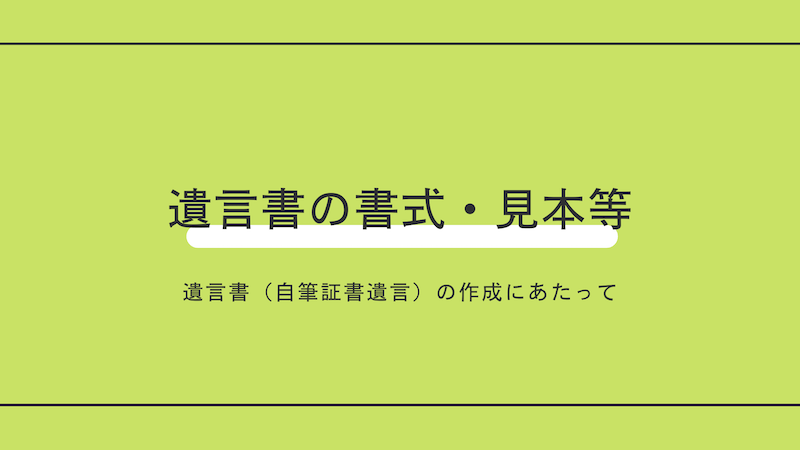
遺言書(自筆証書遺言)の作成にあたって
ここでは、法務局における自筆証書遺言書保管制度(令和2年7月10日施行)を利用することを想定し、遺言書の作成にあたって注意すべき事項等をご紹介します。
なお、法務局では、遺言書の内容に関する相談には応じてもらえません。
遺言書の内容について不明な点がある場合には、まずは弁護士にご相談することをお勧めします。
民法で定められた要件について
遺言書の作成に当たり、必ず守らなければならない要件は以下のとおりです。
- ① 遺言書の全文、遺言の作成日付及び遺言者氏名を、必ず遺言者が自書し、押印します。
遺言の作成日付は、日付が特定できるよう正確に記載します。
例)「令和3年3月吉日」は不可(具体的な日付が特定できないため)。 - ② 財産目録は、自書でなく、パソコンを利用したり、不動産(土地・建物)の登記事項証明書や通帳のコピー等の資料を添付する方法で作成したりすることができますが、その場合は、その目録の全てのページに署名押印が必要です。
- ③ 書き間違った場合の訂正や、内容を書き足したいときの追加は、その場所が分かるように示した上で、訂正又は追加した旨を付記して署名し、訂正又は追加した箇所に押印します。
参考条文
(自筆証書遺言)
民法968条 自筆証書によって遺言をするには、遺言者が、その全文、日付及び氏名を自書し、これに印を押さなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、自筆証書にこれと一体のものとして相続財産(第997条第1項に規定する場合における同項に規定する権利を含む。)の全部又は一部の目録を添付する場合には、その目録については、自書することを要しない。この場合において、遺言者は、その目録の毎葉(自書によらない記載がその両面にある場合にあっては、その両面)に署名し、印を押さなければならない。
3 自筆証書(前項の目録を含む。)中の加除その他の変更は、遺言者が、その場所を指示し、これを変更した旨を付記して特にこれに署名し、かつ、その変更の場所に印を押さなければ、その効力を生じない。
自筆証書遺言書保管制度で求められる様式等
民法上の要件に加え、自筆証書遺言書保管制度を利用する場合に、守らなければならない様式のルールがあります(法務局における遺言書の保管等に関する省令別記第1号様式)。
① 用紙について
- サイズ:A4サイズ
- 模様等:記載した文字が読みづらくなるような模様や彩色がないもの。一般的な罫線は問題ありません。
- 余白:必ず、最低限、以下の余白をそれぞれ確保してください。
- 上5mm 下10mm
- 左20mm 右5mm
- ※ 余白が確保されていない場合や、余白に1文字でも何らかの文字等がはみ出してしまっている場合は、書き直しをする必要があります。
② 片面のみに記載
用紙の両面に記載して作成された遺言書は利用できません。財産目録も同様です。
③ 各ページにページ番号を記載
ページ番号も必ず余白内に書いてください。
例)1/2、2/2(総ページ数も分かるように記載してください。)
④ 複数ページある場合でも、ホチキス等で綴じない
スキャナで遺言書を読み取るため、全てのページをバラバラのまま提出します(封筒も不要です。)。
自筆証書遺言書保管制度で求められる遺言書の記載上の留意事項
さらに、自筆証書遺言書保管制度を利用するための遺言書の記載上の留意事項等があります。
① 筆記具について
遺言書は、長期間保存されますので、消えるインク等は使用せず、ボールペンや万年筆などの消えにくい筆記具を使用してください。
② 遺言者の氏名は、ペンネーム等ではなく、戸籍どおりの氏名(外国籍の方は公的書類記載のとおり)を記載しなければなりません。
※ 民法上は、本人を特定できればペンネームでも問題ないとされていますが、自筆証書遺言書保管制度では、遺言書の保管の申請時に提出する添付資料等で、申請人である遺言者本人の氏名を確認するため、ペンネーム等の公的資料で確認することできない表記である場合は利用できません。
見 本
PDF 遺言書本文(全て自書しなければならない)[サイズ:77KB]
【 ダウンロード 】
PDF 財産目録(署名部分以外は自書でなくてもよい)[サイズ:82KB]
【 ダウンロード 】
ケース別遺言書の記載例
遺言者がおかれた状況は様々であり、遺言書の具体的な内容は事案ごとに異なります。以下は、よくあるケース別の遺言書の記載例となります。
相続人間の円満な関係を考慮した書き方(相続分の指定)
遺言書で各相続人の相続分を指定し、具体的な相続財産の取得については相続人間での遺産分割協議に任せる内容です。
相続人として妻Aのほかに子B〜Dがいるケース
なお、遺言書の冒頭には、家族に対する最後のメッセージや遺言者の希望等を記載しています(付言事項)。
PDF 遺言書 記載例[サイズ:52KB]
【 ダウンロード 】
相続人間の円満な関係を考慮した書き方(遺産分割方法の指定)
妻Aには安心して老後の生活を送れるように自宅を残し、それ以外の財産については子供2人(B・C)に分け与え、祭祀承継者を長男Bと定める内容です。
PDF 遺言書 記載例[サイズ:58KB]
【 ダウンロード 】
子がいない場合の書き方
遺言者には子がいないため、妻Aに全財産を残し、万が一、妻Aが先に亡くなった場合には甥Dに相続させる内容です。
PDF 遺言書 記載例[サイズ:35KB]
【 ダウンロード 】
子に全財産を相続させる書き方
遺言者には妻Aと子Bがいるものの、妻Aとは家庭内別居状態であるため、子Bに全財産を相続させ、付言事項として妻Aに遺留分侵害額請求をしないよう求める内容です。
PDF 遺言書 記載例[サイズ:42KB]
【 ダウンロード 】
特定の人に全財産を引き継ぐ書き方
遺言者には妻も子もおらず、兄弟とも疎遠であるため、長年お世話になってきた知人Eに全財産を遺贈する代わりに、葬儀などを行ってもらう内容です。
なお、知人Eは遺言者の道徳的宗教的希望を託されたのみで法律上の義務を負担するものではなく、遺言書に従った葬儀等を行わないからといって法律上強制することはできない(宇都宮家裁栃木支部昭和43年8月1日審判・判タ238号283頁)と解される可能性があるため、知人Eにはあらかじめ意向をきちんと確認しておく必要があります
PDF 遺言書 記載例[サイズ:42KB]
【 ダウンロード 】
遺産の種類別の記載例
以下は、遺言書に遺産の内容を特定して記載する場合の、遺産の種類別の記載例となります。
不動産
対象不動産を特定して認識できる程度に、不動産登記事項証明書の表示のとおりに記載します。
土地の場合
「所在」「地番」「地目」「地積」
建物(区分建物を除く)の場合
「所在」「家屋番号」「種類」「構造」「床面積」
※附属建物の表示がある場合
「符号」「種類」「構造」「床面積」
区分建物の場合
一棟の建物の表示
「家屋番号」「建物の名称(建物の番号)」「種類」「構造」「床面積」
専有部分の建物の表示
「家屋番号」「建物の名称」「種類」「構造」「床面積」
敷地権の目的たる土地の表示
「土地の符号」「所在及び地番」「地目」「地積」
敷地権の表示
「土地の符号」「敷地権の種類」「敷地権の割合」
※「建物の名称(建物の番号)」があるときはその旨記載する。その場合は「種類」「構造」「床面積」の記載は不要。
エ 所有者が複数の場合や物件ごとに所有者が異なる場合
各物件の末尾に所有者の情報(名前・持分等)を記載する。
「所有者 ○○○○」
「共有者 ○○○○ 持分○○分の○
共有者 ○○×× 持分○○分の○」
1 土地
所在 ○○区○○町○丁目
地番 ○番○
地目 宅地
地積 ○○○○.○○平方メートル
所有者 ○○○○
2 建物(土地所有者○○○○、建物所有者○○○○及び○○××共有)
所在 ○○▲丁目○番地
家屋番号 ○○番○
種類 居宅
構造 鉄骨造2階建
床面積 1階 ○○.○○平方メートル
2階 ○○.○○平方メートル
共有者 ○○○○ 持分○○分の○
共有者 ○○×× 持分○○分の○
1 土地
所在 ○○▲丁目○番
地番 ○番○
地目 宅地
地積 ○○○○.○○平方メートル
共有者 ○○○○ 持分○○○○○分の○○○
2 区分建物(敷地権の登記なし・土地及び区分建物所有者○○○○)
(一棟の建物の表示)
所在 ○○▲丁目○番地○
構造 鉄骨造一部鉄骨鉄筋コンクリート造陸屋根11階建
床面積 1階 ○○○.○○平方メートル
2階ないし11階 各○○○.○○平方メートル
(専有部分の建物の表示)
家屋番号 ○○▲丁目○番○の○
建物の名称 ○○○号
種類 居宅
構造 鉄骨造1階建 床面積 ○階部分 ○○.○○平方メートル
1 区分建物(敷地権の登記あり・区分建物所有者○○○○及び○○××共有)
(一棟の建物の表示)
所在 ○○▲丁目○番地○
建物の名称 ○○○○マンション
(専有部分の建物の表示)
家屋番号 ○○▲丁目○番○の○
建物の名称 ○○○号
種類 居宅
構造 鉄骨造1階建
床面積 ○階部分 ○○.○○平方メートル
(敷地権の目的たる土地の表示)
土地の符号 1
所在及び地番 ○○▲丁目○番○
地目 宅地
地積 ○○○.○○平方メートル
(敷地権の表示)
土地の符号 1
敷地権の種類 所有権
敷地権の割合 ○○○○○分の○○○
共有者 ○○○○ 持分○○分の○
共有者 ○○×× 持分○○分の○
預貯金
預金については、名義人、金融機関名、取扱支店名、預金の種類(普通、定期、当座、貯蓄)、口座番号を記載して特定します。
貯金についても、預金と同様に特定して記載します。貯金の種類(通常貯金、通常貯蓄貯金)、記号・番号によって特定します。なお、ゆうちょ銀行は、他の金融機関からの振込用に、銀行と同じ取扱支店名、預金の種類、口座番号が割り振られているので、こちらを記載しても大丈夫です。
【預金】
1 ◯◯銀行◯◯支店 普通預金 口座番号◯◯◯◯ 名義人甲野太郎
2 □□銀行□□支店 普通預金 口座番号◯◯◯◯ 名義人甲野太郎
【貯金】
1 通常貯金 記号◯◯◯◯ 番号◯◯◯◯ 名義人甲野太郎
2 通常貯蓄貯金 記号◯◯◯◯ 番号◯◯◯◯ 名義人甲野太郎
株式
上場株式については、会社名等で特定するか、口座のある証券会社等によって特定します。非上場株式については、会社名、株式の種類等によって特定します。
【上場株式】
口座開設者 ABC証券株式会社(○○県○○市○○町○丁目○番○号)
加入者 甲野 太郎
口座番号 ○○○○
銘柄 ○○株式会社普通株式
銘柄コード番号 ○○ 数量 1000株
【非上場株式】
会社名 ◯◯株式会社
券 種 普通株式
記 号 ◯◯
番 号 ◯◯ 数 量 ◯◯株
投資信託
投資信託に係る信託契約に基づく受益債権については、共同相続された場合、相続開始と同時に当然に応じて分割されることはない(最判平成26年2月25日・判タ1401号153頁)とされていますが、一部解約実行請求は可能とされている商品が通常ですので、遺言書において、割合的か特定額かで分割して遺贈することも可能です。なお、投資信託によっては、1口単位ではなく、1000口単位で取引されるものもありますので、遺言するに際しては、事前に銀行や証券会社に問い合わせた方が良いでしょう。
投資信託
口座開設者 ABC証券株式会社(○○県○○市○○町○丁目○番○号)
加入者 甲野 太郎
口座番号 ○○○○
名称 ○○ファンド
委託者 ○○株式会社
受託者 ○○信託銀行株式会社
銘柄コード ○○
国債
個人向け国債についても、共同相続された場合、相続開始と同時に当然に応じて分割されることはない(最判平成26年2月25日・判タ1401号153頁)とされています。個人向け国債は、相続により当然分割される可分債権ではありませんが、解約して償還期限前でも現金に換えることができ(中途解約のできない据え置きの時期でも相続の場合はできます。)、その一部の償還も認められます。遺言では、例えば額面1000万円の国債を500万円ずつ遺贈、相続させることができます。
○年利付国債
口座開設者 ABC証券株式会社(○○県○○市○○町○丁目○番○号)
加入者 甲野 太郎
口座番号 ○○○○
名称 利付国庫債券
記号 第○回
金額 ○○万円
年利率 0.8%
利払日 毎年○月○日及び○月○日
償還期限 ○年○月○日
生命保険契約
生命保険契約については、相続させる保険契約を特定するために、保険証券のとおりに記載します。
保険証券番号 ◯◯◯◯◯◯◯◯
保険契約日 ◯◯年◯◯月◯◯日
種類 ◯◯養老保険
保険期間 ◯年
保険金額 ◯◯万円
保険者 ◯◯生命保険相互会社
契約者 甲野太郎
被保険者 甲野太郎
満期保険金受取人 ◯◯
生命保険金受取人 ◯◯
また、遺言による保険金受取人の変更の可否について、平成22年4月1日施行の保険法は、遺言で変更できると規定しました(保険法44条1項)。
ただし、遺言による保険金受取人の変更は、その遺言が効力を生じた後、保険契約者の相続人がその旨を保険者に通知しなければ、保険者に対抗することができません(同条2項)。
また、契約者と被保険者が別の場合、死亡保険契約の保険金受取人の変更は、被保険者の同意がなければ、その効力を生じないとされています(同法45条)。
遺言によって生命保険の受取人を変更する場合、新たな受取人は、原則として保険約款等で定められる者の範囲内で決定する必要があります。
一般的には、配偶者と一定の血族に限定されているケースが多いです。
保険約款等における規定の範囲内であれば、生命保険の受取人を相続人以外の第三者に変更することもできます。
また、保険商品の内容等によっては、親族関係のない第三者(内縁の妻・お世話になった人・慈善団体など)を受取人に指定できるケースもあります。
生命保険の受取人変更の範囲については、あらかじめ保険会社にお問い合わせください。
以下は、遺言で保険金受取人を変更する場合の記載例です。
第◯条 遺言者は、次の保険契約に関する保険金の受取人を、長女B(◯年◯月◯日生)に変更する。
保険証券番号 ◯◯◯◯◯◯◯◯
保険契約日 ◯◯年◯◯月◯◯日
種類 ◯◯生命保険
保険期間 ◯年
保険金額 ◯◯万円
保険者 ◯◯生命保険相互会社
契約者 甲野太郎
被保険者 甲野太郎





